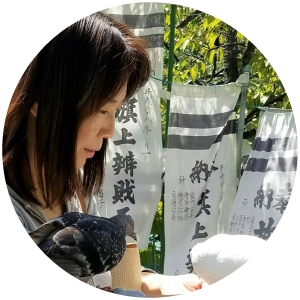■前回のあらすじ
「大船」の地名の由来をさぐると、たいていの書籍では「古地名の「粟船(あわふね)」が変化したもの」と書かれている。それを踏まえて、次の疑問が浮かび上がった。
㋑ 大船周辺に「粟を載せた船が着岸」するほどの水辺があったのか。
㋺ なぜ「粟」を載せた船なのか。船が入れるほどの水辺があったのであれば例えば「船津」みたいな地名でも良かったのではないか? 船にわざわざ粟を冠する理由はなんだったのか?
㋩「アハフナ(あわふな)」が、なぜ「オホフナ(おーふな)」になったのか。確かに「似ている」と強弁されればそういう気になるものの、でも「あわ」と「おー」はずいぶん差があるのでは?
今回は、以上の謎を考察したい。
それではまず、㋑の疑問について調べてみたい。
『鎌倉市史』を紐解くと、その疑問はすぐに解けた。こちらの画像を御覧いただきたい。

縄文時代の海岸線(『鎌倉市史』より)
これは、縄文時代の鎌倉周辺の海岸線のようすだ。海が今よりも内陸側にぐいっと入りこんでいる。ちょっと信じられないけれど、柏尾川に沿うように入江が戸塚のあたりまで入り込んでいる。

海抜の表示
大船駅から常楽寺へ向かう途中にあった海抜表示はおよそ9.4メートル。上記の地図ではこのあたりも入江となっているので、縄文時代はいまより、すくなくとも9メートルは海面が高かったのだろう。
縄文時代には海の底であった粟船(大船)周辺だが、その後、海岸線はずっと後退し、海とかなり離れたものの、土地が低いことには変わりなく、相変わらず葦の生い茂る湿地だったという。明治20年(1887年)柏尾川の東に東海道線が開通し、横須賀線が着工されると、大船駅が開業する。駅自体は横須賀線との乗り換え客で賑わうようになるものの、この頃においても、大船駅前は葦の原と田んぼばかりで人家はほとんどなかった。

大正時代の地図

昭和時代の地図
湿地と田んぼばかりだった大船駅前に人家が建ち始めるのは昭和に入ってからだ。しかし、水が溜まりやすいという地形は変えがたく、大船の町は水害にたびたび見舞われたという。
大船で自転車店を営んでいた佐々木泰三氏が、自らの自伝と、大船の歴史について記した『水の出る街、大船』によると、昭和の中ごろにはほぼ毎年、町が水に浸かるという被害を受け、とくに昭和36年(1961年)6月の豪雨災害は被害が大きく、柏尾川が氾濫し大船地区だけで床上浸水1818戸、床下浸水4905戸という大きな被害が出ている。
海からずいぶん離れているとはいえ、水が溜まりやすい地形であることは、時代が下った現代でもそうなのだ。
話がすこしそれてしまったが、つまり「粟船」の地名がついたころは、船が出入りできるほどの水辺が、粟船(=大船)にはあったということがわかった。
なぜ粟なのか
さて、残りの謎、㋺、㋩である。
㋺ なぜ「粟」を載せた船なのか。船が入れるほどの水辺があったのであれば例えば「船江」や「船津」みたいな地名でも良かったのではないか? 船にわざわざ粟を冠する理由はなんだったのか?
㋩「アハフナ(あわふな)」が、なぜ「オホフナ(おーふな)」になったのか。確かに「似ている」と強弁されればそういう気になるものの、でも「あわ」と「おー」はずいぶん差があるのでは?
あらかじめ結論を述べておくと、このふたつの謎に関しては「わからない」ということしかいえない。地名のゆらいに関しては、そう決めたという文書なりが残っていることが、とても少なく、断言できない場合も多い。大船に関してもそうだろう。
しかし、ここはあえて、筆者の独断と偏見でもって、大船の地名の由来を、もっとツッコんで考えてみたい。
まず㋺に関して、船が出入りできるほどの水辺があり、実際に船が出入りしていたとしても、なぜ粟の船なのか。
確かに、粟は縄文時代にはすでに日本に伝わっており、栽培もされていた日本最古の作物のひとつされている。そういういみで、地名に粟がつくのは自然で納得できる。実際、阿波国の阿波は粟がゆらいという説もある。
しかし、船が連なっているという風景を言うのに、なぜわざわざ「粟を積んだ船」と形容しなければならなかったのかが、わからない。
そして、㋩の謎。「粟船(あわふな)」が「大船(おおふな)」に変化した謎もわからない。「粟船が大船になった」ということを言われれば、ついうっかり「なるほど」なんて思ってしまうが「あわふな」が「おおふな」である。漢字も全く違うし、発音もかなり違うのではないか。
本稿冒頭でも紹介したが、粟船が大船として文献に登場するのは、江戸時代である。もう少し詳しくみていくと、正保元年(1644年)に幕府が作成した『諸国郷村高帳』に「大舟」と出てくるのが最初で、江戸時代中ごろまでは「粟船」「大舟(船)」がどちらも使われていたようだ。「大船」の表記が定着したのは18世紀に入ってからで、江戸時代後期から幕末にかけてはすでに「大船」となっている。
これらの謎は、記録が残ってないかぎり、わからないとするか、残っている資料からある程度推測するしかない。
ここからさきは、素人である筆者の推測、想像であり、学問的な裏付けなどがあるわけではないことをお断りしておきたい。
㋺の謎にかんしては、おそらく、粟を積んだ船というのはよくある語源説話のひとつで、「粟船(あわふね)」の本当のゆらいは地形をあらわす言葉だったのではないだろうか。
「あわ」という言葉に関しては、さまざまないみがある。『日本地名辞典』(新人物往来社・吉田茂樹)によると、西日本を中心に、海岸地方に存在するアワには、もともと「網場(アバ)」(漁網を干す場所)といういみもあり、漁業民に関連するいみがある可能性があると指摘している。
また『地名用語語源辞典』(東京堂出版・楠原佑介)によると、"アワ(泡、沫)で、やわらかい。はかない。しっかりしない」意で、「湿地」などを表す用語か"とある。
例えば、精製していない固い塩のことを「堅塩(カタシホ)」といい、それに対し、精製した柔らかい塩を「淡塩(アハシホ)」というように、やわらかいことを「アワ」ということがあるのだ。
さらに、フネに関してみると、ウネ(畝)が、フネに転訛した例もおおい(『日本地名辞典』)という。ウネとは畑の畝のように、土地が細長く盛り上がった場所のことだ。
つまり、湿地帯の中にあって、細長く盛り上がった場所、アワウネが、変化して、アワフネ、粟船となった......という見立てはどうだろう。常楽寺の後ろにある小高い「粟船山」は、ウネというのにピッタリな細長い丘である。

地理院地図
残った㋩の謎に関しては、まったくもって手がかりがない。アワフネを早口で10回ぐらい唱えてみると、たしかに「オーフナ」みたいになるのは認めるが、それにしても......である。
これも筆者である私の勝手な妄想と推測なのだが、粟船が大船と書かれるようになったのは、瑞祥地名のようなものではないだろうか。
江戸時代は「新堀」が「日暮里」になったり、「埋田」が「梅田」になったように、地名にわざと風流だったり、めでたい当て字をすることがよくあった。
つまり、こういうことである。江戸時代の後期にもなると、稲作の技術が発達し、弥生時代や鎌倉時代に比べると、白いご飯は農民でもずいぶん食べられるようになっていたはずだ。そんな時代に、いつまでも粟の船の「粟船」を名乗るよりも、大きな船の「大船」の方が、なんだか、めでたい気がするので、書き換えた......という可能性だ。
江戸時代の人たちは「粟」よりも、画数が少なく、発音も似ており、すこし、めでたいいみがある「大」に書き換えるていどのことは、躊躇しなかっただろう。
なんどもいうが、上記の推測は、もちろん、学問的な裏付けがある説でないことは、改めて申し述べておく。
つまり、私が開陳した、大船地形由来説も、確かな根拠があるものではないので、あくまで想像の範囲でしかなく、つまり「大船はなぜ大船になったのか」ということについては「わからない」ままである。