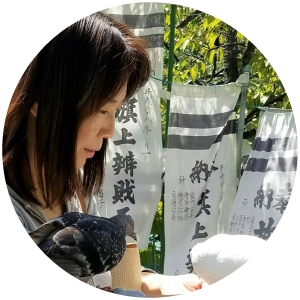illustration by 猪原美佳
昼どきの賑わいを控えた、午前10時前。商店街はお客を迎える準備で慌ただしい。空になった段ボールが宙を舞い、山積みになっていく。店先は、箒で掃き清められる。出来立ての惣菜が、ショーケースに並ぶ。舞台は整った、さあどんな一日が始まるだろう。
仲通りの真ん中、商店の娘に生まれたわたしは、幼い頃から鍵を勝手に開けては家を飛び出し、商店街に遊んだ。仕事の手つきを見るのが楽しみだった。ケーキ屋さんのお姉さんが、袋を絞ってチョコレートで文字を書く。卵屋の腰の曲がったおばあさんが、かごに盛られた卵を新聞紙に載せ、指先をペロッと舐めてくるりくるりと包んでいく。八百屋のおじさんがお釣りをひょいっと、頭上の籠に投げ入れる。ひとつひとつの仕事には、子供の目には魔法じみて映る手つきがあって、店の前に突っ立っては飽きず眺めた。
30年近くが過ぎ、店の並びも様変わりした。わたしは今もなお、商店街を歩くのが大好きだ。それぞれの店には、それぞれの「魔法じみた」技があり、商品があり、人がいて、価格があり、それらはどれも誇らしそうに「これからくる人を、喜ばせるためにある」という感じがするから。どうです?新鮮でしょう。美味しそうでしょう。綺麗でしょう。それらが並ぶ商店街は、本当に楽しく、美しい。
そして商店街からバス通りに出れば、大船にはあの柔和な笑みがある。観音さま。大船小学校の写生の定番といえば、観音さまだった。首から画板を下げて、思い思いに観音さまを描く。あの流れるような線が、難しい。教室の後ろに貼られた30枚の観音さまは、やけにスマートだったり、灰色に塗られてお地蔵さんみたいだったり。どれもやっぱり、どこか違って。あのお顔に見守らていることを当たり前に育ってきたから、電車の車窓、真っ白なお姿が見えると、あぁ、帰ってきたと心底ほっとするのだ。
夕暮れ時。ふいに、誰かの不在が胸にくる。店先でお酒を飲みながら街のにぎわいを眺めていた、豆腐屋のおじさんのいいお顔。間口からのぞいた、魚を捌く真剣な横顔。角で出迎えてくれた色豊かな果物屋さんや、幼い日に浴衣を仕立ててもらった呉服店。たとえもう姿が見えなくとも、この街に生きて、残していった人たちのことを、わたしは知っている。大船はきょうも元気です。そう、語りかけたくなる。(陽)